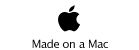単身赴任
昔、お国のためにいとしい妻子を故国に残して戦地に赴くのを「出征」といった。今、妻子を故郷に残して任地に赴くのを「単身赴任」と言う。
*
やっと建てたマイホームの管理上、子供の学校の都合上・・・理由はいろいろあるが、いずれにしても、それら総てのシワヨせを、亭主ひとりが一身に背負って単身・任地に赴任していく・・・。
昔は、「夫婦に子供」これは離れられない最小単位で、亭主が一人離れて働きながら炊事、洗濯をするなどということは考えられないことだった。強いて分離するとすれば、子供を離して下宿させるというテであったろう。しかし今は昔と違って、マンション・冷蔵庫に洗濯機の普及、インスタント食品、スーパーマーケット、コンビニなどの発達で、女房族の存在価値が低くなったことは否めない。
*
単身赴任者は自嘲をこめて、自分ことをスーパー通いのスーパーマンと言ったりしているが、或る先輩が海軍時代の同期会で、「俺は今単身赴任中だ」といったら、 ”何と幸せな”・・・と皆に羨ましがられたという。この人は週末に家に帰り、週明け任地に向かう自分を、「半身赴任」といい ”出稼ぎに・・・”と言って家を出ると笑っていたが、本当にそんな感じなのだろう。
*
俗に”男やもめに蛆が湧く”というが、そんなことはない。この単身赴任者、意外としっかりしているものである。火・木・土のナマごみの日、ポリ袋をつまんで玄関を出る時の姿にはやや悲哀を感じるが、例外なしに身奇麗だし、ゴルフの朝がどんなに早かろうとちゃんと時間には支度ができて待っている。
勿論、単身赴任といっても時に奥さんが訪ねてこられて、暫し逗留されることも有るわけだが、服装にしろ付き合いにしろ、奥さんが来ておられるのか、いつもの通り単身なのか亭主を見ているだけでは全く区別がつかないくらいなのである。
*
そこである日愚問を発してしまった。”今、奥さん来ておられるの?”・・・。彼曰く”女房が来ていたら、こんなに色艶がいい訳ないでしょう・・・。
やはり”女房達者で留守がいい?”ということか。
味 噌 汁
N園のトップ商品に ”A”というインスタント味噌汁がある。これが出来たとき、そこの社長さんは、これはあんまり売れないだろうと、さして期待していなかったという。
何故ならば、その社長さんの年代の感覚では、朝のみそ汁は、その家の一日の始まりのしょっぱなの夢である。トントントンと葱を刻む音、ほんわかと洗面所まで漂ってくる味噌のかおり、今日のミは豆腐かな、わかめかな?・・・使う味噌も家によってあまみそ・からみそ・しろみそ・・・何によらず子供の頃から育てられた、その家の手作りの伝統があるものだ。この嗜好はそうインスタントに覆すことは出来まいと思ったからだという。
*
ところが、あけてびっくり玉手箱!。案に相違してそのインスタント味噌汁が売れに売れたという。そこで、買ってくれる若夫婦を対象に市場調査。・・・何故この ”A”を愛用するのか。アンケートの結果一番多かった回答。
妻「朝は五分でも長く床に入っていたいから」。
夫「妻の作る味噌汁より、この方がうまいから」。
受 験 生
ある赤提灯のおかみの話。
「常連の課長さんとその部下の方が、どこで飲んだのか、もう大分出来上がって、肩を抱きあってのれんをくぐってこられました。どちらもいいご機嫌で和気藹々。飲むほどにますます調子が出てきたところで、その課長さんがふと膝をたたいて ”そうだ、俺のうちにいいウイスキーがあるんだった。まだ大分残っているからオイロナオシに、それでやろうじゃないか””いいですね。ご馳走になります” ”オイ、おかみ電話を貸してくれ”と大変な勢いでお宅へ電話されたんです」。
*
「あとは、どういうやり取りか向こうの声は聞こえないので想像ですが、どうやら話の筋は、家に受験期のお子さんがいらして、期末試験の最中だと言うことで、奥さんに断られている様子ーーー。
ところが、こちらは酔っているし、第一今さら部下の前で引っ込みがつかない。小さな声もだんだん大きくなって、おこったり、さとしたり、しまいには ”決して大きな声は出さないから・・・”と哀願調に変ったが、結局勝負は奥さんの勝ち」。
*
「聞こえない振りをしていた部下の方が、わざと酔ったロレツで ”もう動くのも面倒だからこのままここでやりましょうよ・・・”と言って下さったんですが、すっかり酔いも冷めて、しょんぼり飲み始めた課長さんに、かける言葉がなくて・・・あんなにバツの悪い思いをしたことはありませんでしたねえ」。
(83・S・58・6)