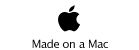旅 館
仕事の関係で、準備してくれた或る地方都市の旅館に泊まった。絶えて久しくホテルーーーそれも羊羹を切ったようなビルで、バスもトイレもまるで缶詰の中に入ったような安直なビネスホテルばかりに宿泊していたのだが、この旅館に泊まって古い日本の良さにあらためて接する思いだった。
*
まず何とも懐かしいのが玄関の叩き、靴脱ぎの自然石の踏み台、板の廊下、床の間の掛け軸に香炉・活花、磨き上げられた床柱・・・。お茶、新聞、食事への仲居さんの気働きもさることながら、”殿のためなら命も捧げる”みたいな忠義一徹そうな爺さんが、さりげなく目だたず外回りのサービスをしてくれる。例えば、帳場に頼んでおいた朝風呂、湯加減・湯量がみごとに加減してあり、朝日が斜めに湯気を横切る湯殿の中に、必要なもの(手ぬぐい、石けん、かみそり、歯ブラシ、手桶・・・etc)が、すべてそれぞれ使う立場の場所にさりげなく置いてあり、上がってきたら、いつのまにか脱いだ上履きが出舟に揃えて置きなおしてある。部屋に戻ると布団が片付けられ、机の上にお茶のセットと朝刊、灰皿にマッチ・・・。
*
”先回りの親切”という。客の気持ちを先さきに汲んだ帳場、仲居さん、雑役さんのこれ見よがしでない、イキの合った気働きの見事さ。
時間と空間をビジネスライクに切り売りするような、ツンとすましたホテルにはない潤いーーー日本人のこうした伝統的な文化も、時の流れとともに博物館的な存在になっていくのだろうなあ。
結 束
自分に軍隊の経験はないが、傍から見ていて、旧海軍出身の人の連帯は、陸軍出身の人よりも強いように思われる。昔、海軍兵学校と同じレベルで陸軍士官学校というのもあったのだが、やはり陸士よりも海兵出身の同期生の結束が固いように思われる。
*
軍隊は、陸・海・空いずれを問わずいわば命をかけてのチームとしての訓練であり戦いである。チームとしての団結は骨のズイまで叩き込まれたに違いないのだが、戦争が終わり何十年か経っての仲間意識が、何故海軍に強く残っているのか?。
*
勝手な推測で申し訳ないが、同じ命がけながら、陸軍・空軍がいってみれば個人で戦功を挙げるチャンスがあり、単独で生死が決定づけられるのに比べ、海軍はすべてが軍艦という危険物のかたまりの上での共同生活ーーー死なばモロとも,戦果もすべて共同のものーーーそんなところから、その差が生じてくるのではないかと思うのだが、どうだろう。
空
また一人親しい友が亡くなった。一年近く病床に伏して少しずつ衰弱して、とうとう逝ってしまった。
人がひとり、目の前で死んでいこうというのに何も出来ないもどかしさ。すべての人は必ず死ぬ。今までも皆死んでいった、だけど誰にも止めることはできなかった。これからも皆死んでいくだろう。とうとうと流れる、誰にも止めることのできない厳然たる事実。そしていずれは自分もその流れの中に没していくのだが。とにかく、今、目の前に死んでいく人がいるのに、手をこまねいているこのもどかしさ。。
*
それでもまだ、不治の病の床といっても、再び起き上がれないと判っていても、とにかく彼が「居る」うちはよかった。「死ぬ」「逝く」「亡くなる」・・・「死」について、いろんな言葉があるけれど、死ぬということは ”無くなる”のである。ある日忽然と、この世から居なくなってしまうのである。何という捉えどころのない「空」であろうか。
*
とうとう友が一人、無くなってしまった。
名 文
「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白くなった」。・・・名文の代表と言われる、ご存知川端康成「雪国」の冒頭の一節である。(余談ながら、ラジオの朗読で これを ”コッキョウの長いトンネル・・・”と読んでいたが、これは頼むから ”クニザカイの・・・”と読んで頂きたい。日本にはコッキョウはありません)
*
さて、次の文は、最近土筆生が心に留まった文章。遠藤周作さんの「女の一生」の中の一節。
「向こうに夕陽が空を真紅に染めていた。それは、夏の一日が終わり、昼が夜を呼ぶ前の絢爛たる別れの挨拶だった」。
何と見事な描写だと思うが、如何?。